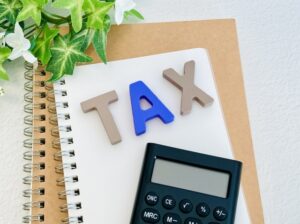『節税=得』ではない!正しい判断の見極め方

「税金を払うくらいなら、経費を使ったほうがマシ」
この言葉、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
一見もっともらしく聞こえますが、実際にはこの考え方が“会社にお金が残らない根本原因”になっていることも少なくありません。
節税は「やればやるほど得になる」ものではなく、使い方を間違えれば「やればやるほど損をする」可能性もあるのです。
本記事では、「節税=得」という思い込みを捨て、本当に意味のある節税と、危険な節税の見極め方を税理士視点でわかりやすく解説します。
なぜ「節税=得」だと錯覚してしまうのか?
多くの経営者が節税に惹かれる理由は、「税金を払うのがもったいない」と感じるからです。確かに、何百万円もの納税額を見ると、「このお金を使えば税金が減るのに」と思ってしまうのは無理もありません。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
仮に100万円の利益に対して30万円の税金が発生するとして、80万円の経費を使えば利益は20万円に減り、税金も6万円で済みます。
このとき、多くの人は「24万円も節税できた」と考えますが、実際には80万円のキャッシュが減っているのです。つまり、24万円の節税のために、80万円を失ったというのが事実です。
この構造を理解しないまま節税に走ると、会社の現金はどんどん減っていきます。
節税が“逆効果”になる3つのパターン
(1) キャッシュフローを悪化させる節税
保険への加入、高額な備品購入など、節税を名目にキャッシュが流出し、資金繰りが苦しくなるケースです。税金は減っても、お金が残らないのでは意味がありません。
(2) 経費の“中毒”になる
節税目的で経費を乱発すると、「経費を使うクセ」がつきます。一度ついた経費体質はなかなか治りません。結果として、利益率が低いまま固定化し、高収益体質とは真逆の会社になります。
(3) 将来の資金ロックを招く節税
例えば、節税目的の法人保険は、解約返戻金を得るまでに時間がかかり、資金がロックされます。経営の柔軟性が奪われ、必要なときにお金が使えないという事態も起こります。
「得になる節税」と「損になる節税」の違いとは?
節税は「手元に残るお金を最大化する」ために行うものです。税金が減っても、使った分以上にお金が出ていれば、それは“損”です。
得になる節税の特徴
- 将来キャッシュを生む投資とセットになっている
- 生産性・利益率が改善する支出である
- 手元資金を減らさない(または将来戻ってくる)
- 節税と経営戦略が一致している
損になる節税の特徴
- とりあえず保険に入る/備品を買う/広告を打つ
- キャッシュが一気に出ていく
- 効果が測定できない、回収できない
- 節税が目的化している
節税を「数字」で見極める習慣を持つ
節税の良し悪しを判断するには、感覚や気分ではなく「数字」で判断することが重要です。
チェックポイント:
- この支出によって、何円の税金が減るのか?
- その代わりに、いくらのキャッシュが出ていくのか?
- 減税額 < 支出額 なら、その節税は“損”
逆に、減税額よりも大きなリターンがある見込みの支出であれば、それは良い節税=戦略的投資です。
「税金を払うこと=損」ではない
節税にばかり気を取られていると、「税金を払うこと自体が悪」と思いがちです。
でも実は、税金を払っているということは、「それだけ利益が出ている」という証拠でもあります。健全な会社ほど、しっかりと税金を払っています。
「税金を払ってでもお金が残っている」状態を目指すことこそ、本当の意味での“強い経営”です。
まとめ:「節税に使う前に、まず問うべき3つのこと」
- この支出は、未来の利益を生むか?
- この節税は、会社のキャッシュを減らさないか?
- この判断は、経営の自由度を高めるか?
この3つの質問に「YES」と答えられる節税だけが、本当に“得”になる節税です。
節税はテクニックではなく、経営判断のひとつです。
あなたの会社にとっての“得”とは何か?
それを見極め、必要なときに必要な節税を選べる経営者こそが、最終的にお金を残し、会社を成長させることができます。