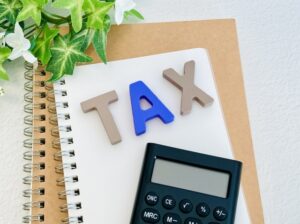利益を圧迫する節税ミス、していませんか?

「税金はなるべく払いたくない」「利益が出そうだから、節税のために何か使わなきゃ」
こうした感情や行動は、中小企業の経営において“あるある”かもしれません。実際、多くの社長が「節税対策=経費を増やすこと」だと思い込み、年度末になるとあわてて支出を増やしがちです。
しかし、それは本当に正しい節税でしょうか?
むしろ、そういった行動こそが会社のキャッシュを減らし、利益を圧迫する“節税ミス”かもしれません。
本記事では、実際によくある失敗例をもとに、「お金が残らない原因」となる節税の落とし穴を明らかにし、正しい判断軸を持つためのポイントをお伝えします。
「節税=経費を増やす」は危険な思い込み
まず最初に、根本的な勘違いを正しましょう。
よくある誤解は、「税金を減らすために経費を使えば得になる」という考え方です。
たとえば、100万円の利益が出そうなときに、80万円分の備品を購入したとします。確かに税率30%だとすると、24万円の税金が減ります。しかし、同時に80万円のキャッシュが出ていきます。
つまり、24万円を節税するために80万円を失っているわけです。これは得でもなんでもなく、むしろ会社の体力を削る行為です。
節税はあくまで「お金を使う手段」であって、目的が「お金を残すこと」からズレてはいけません。
節税という言葉に惑わされて、経費の正当性や将来へのリターンを検証しないまま支出してしまうことが、中小企業の経営をジワジワと苦しくする最大の原因の一つです。
よくある節税ミス5選(+1)
(1) 不要な高額備品の購入
「どうせ買うなら決算前に」と、無理に高額な備品や機械を購入していませんか?本当に今必要なものなら良いですが、先送りできる支出を前倒しにしてキャッシュを減らすのは、本質的な経営判断ではありません。
(2) 節税目的の保険加入
法人保険は節税効果があると言われていますが、実は「戻ってくるのは何年も先」「途中解約で元本割れ」「解約返戻金に税金がかかる」など、デメリットも多くあります。税理士に勧められるままに加入して後悔するケースも少なくありません。
特に、複雑な保険商品は経営者が内容を正確に理解できていないまま契約してしまうケースが多く、思ったような節税効果が得られず、キャッシュが拘束されたまま数年間放置されてしまうこともあります。
(3) 無意味な広告費・交際費の増加
「領収書さえあれば経費になるから」と、必要性の低い接待や広告を増やすこともありがちなミスです。売上につながらない経費は、単なる浪費であり、会社のキャッシュを圧迫するだけです。
特に、WEB広告やポスティングなど、効果測定が曖昧な施策に多額の資金を投じる場合は、費用対効果を十分に精査する必要があります。
(4) 固定費の増加を促す節税
節税のために人を雇ったり、新規の事務所を借りたりといった固定費の増加は、来期以降の経営を圧迫します。節税はあくまで一時的な話なのに、固定費は恒常的に会社の負担となります。
「節税のために固定費を増やす」というのは、典型的な“将来にツケを残す”経営判断です。
(5) 節税ばかりに気を取られて「資金繰り」を見落とす
「税金は減ったが、なぜか資金繰りが苦しい」というケースは、節税だけに意識が向き、キャッシュフロー全体を把握できていないことが原因です。節税だけに集中しすぎると、事業全体のバランスが崩れていきます。
(6) 節税が“目的化”してしまっている
節税とは本来「利益を守る手段」です。しかし、その行為自体が目的になると、税金を減らすために会社を弱らせてしまいます。「節税して満足」ではなく、「節税して利益・キャッシュを残す」ことが本来の目的です。
正しい節税判断のための3つの視点
(1) 節税が“未来の利益”に繋がっているか?
節税支出が「将来的に売上や利益を生む」のであれば、それは戦略的投資です。逆に、まったく回収の見込みがない支出は“節税に名を借りた浪費”です。
未来への投資になるかどうかは、「この支出がどういう形で回収されるか?」を明確に描けるかどうかで判断できます。
(2) 節税とキャッシュのバランスは取れているか?
「税金は減ったけど現金が減った」なら、それは本末転倒です。節税のためにお金を使うときは、常に「手元資金が減りすぎないか?」を確認しましょう。
資金繰り表を自分の手で書いてみることで、キャッシュの流れを実感できるようになります。Excel任せでは見えない数字の実態が、ここで明らかになります。
(3) 節税が「経営の自由度」を奪っていないか?
保険や高額設備への偏った節税は、将来の資金ロックにつながります。現金が減れば、チャンスへの投資や、万一の備えが難しくなり、経営の柔軟性が失われます。
資金は“動かせる状態”にあることが経営の柔軟性を生みます。節税のためにキャッシュを縛ることは、リスク対応力の低下を意味します。
じゃあ、どう節税すればいいのか?
■ 売上に直結する経費だけを選ぶ
広告、販促、営業強化、人材教育など、「今の支出が来年の売上を生むか?」を判断基準にしてください。そうすれば、その経費は“投資”であり、結果的に税金も抑えられます。
■ 減価償却資産の使い方を戦略的に
即時償却できる制度(中小企業経営強化税制など)を活用しながら、資産形成と節税を両立させましょう。機械、ソフトウェア、設備など、将来の収益に貢献する資産を選ぶのがコツです。
■ 将来の備えをしながら節税する
倒産防止共済、小規模企業共済などの制度は、一定の条件を満たせば損金算入でき、将来のための“備え”にもなります。出口戦略まで見越した活用が重要です。
これらの共済制度は、短期的な節税と長期的な資金保全を両立させる数少ない手段の一つです。資金の“待機場所”としても非常に有効です。
まとめ:「節税=得」とは限らない
節税をすれば得をする。
そう信じている経営者ほど、お金を残せていないのが現実です。大切なのは「税金を減らすこと」ではなく、「会社にお金を残すこと」。
そのためには、
- 節税の本質を理解し
- お金が減らない判断を優先し
- 将来の利益を生む使い方を選ぶ
この3点を常に意識してください。
節税の“罠”にハマるのではなく、キャッシュを守りながら会社を強くしていく。これこそが、真に意味のある節税戦略です。