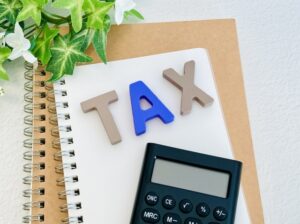キャッシュが残る節税の本質とは?

「頑張って売上は伸ばしているのに、なぜか口座残高が増えない…」。
こうした悩みを抱える中小企業経営者の方は、実は非常に多いです。努力の成果として数字上の売上は順調に伸びている。けれども、なぜか月末になると資金繰りに苦しんでいる。そんな現実に、疑問と不安を感じていませんか?
このような現象が起こる背景には、「キャッシュ(現金)と利益の違いを正しく理解していないこと」があります。そしてもう一つ、見落とされがちなのが「節税の考え方の誤解」です。
本記事では、税理士の視点から「キャッシュを残す節税」の本質と、そこに至る実践的な考え方をお伝えします。利益を増やしつつも、ちゃんとお金が残る会社になるための第一歩にしてください。
節税とは「キャッシュを残すこと」ではない?
まず最初に、多くの経営者が勘違いしているのが「節税すればお金が残る」と思い込んでいる点です。
結論から言うと、節税=支出です。
例えば、決算前に慌てて高額な備品を買ったり、必要以上の保険に加入したりするのは、典型的な「キャッシュが減る節税」です。税金は減るかもしれませんが、それ以上にお金が出ていっているのが現実です。
つまり、「税金を払う代わりにお金を使っている」だけであり、本質的には資金繰りの改善にはつながっていません。
もっと問題なのは、こうした行動が「節税して得した」という誤った成功体験として経営判断のクセになってしまうことです。何度も繰り返すうちに、税金は減ったけれどキャッシュがなくなった、という悪循環に陥っていきます。
税金を減らすことが目的化してしまうと、経営判断が「いかにお金を使うか」という視点になり、本来考えるべき「どうやって利益を増やし、キャッシュを厚くするか」という視点が薄れてしまいます。
利益とキャッシュは別物
会計上の利益と、実際に手元に残る現金はイコールではありません。これは経営者が理解しておくべき最重要ポイントの一つです。
例えば、売上は立っていても「未回収(売掛金)」であれば現金は増えていないからです。また、設備投資や在庫の仕入れなど、利益にすぐには反映されない支出も多く存在します。
法人税が発生するのはあくまで「利益」に対してであり、キャッシュの増減とは必ずしも一致しません。そのため、利益が出ているにもかかわらず、「資金繰りが苦しい」という事態が起きるのです。
ここに節税支出が加わると、さらにキャッシュフローは悪化します。つまり、売上が増えて、利益も出ていて、税金も抑えているのに、「現金だけがなぜか足りない」状態に陥るのです。
結果的に、自社のキャッシュフローを改善するために借入をせざるを得ないという本末転倒な状態になることもあります。
節税は「戦略的」に行うもの
ここで考えてほしいのが、「お金を減らさずに、将来につながる形で節税する方法があるか?」という視点です。
たとえば、次のような考え方が重要になります。
- 無駄な支出を減らし、本当に必要な設備投資に絞る
- 利益圧縮型の節税ではなく、資産形成型の節税を優先する
- 税制優遇を活用して「使う予定のある投資」を前倒しで実施する
よく使われるのが「中小企業経営強化税制」など、一定条件を満たすと即時償却や特別償却が可能になる制度です。これを活用すれば、将来に役立つ設備を導入しながら、節税とキャッシュのバランスをとることができます。
また、「倒産防止共済」などを活用することで、将来の万が一に備えながらも、一定の範囲で損金算入が可能になる節税方法もあります。ただし、これも「本当に必要な備えかどうか」を冷静に判断する必要があります。
キャッシュを守る3つの鉄則
節税=キャッシュの浪費にならないように、次の3点を意識してください。
(1) 節税の目的を「手元資金を厚くすること」と再定義する
「税金を減らすこと」ではなく、「使えるお金を最大化すること」が本来の節税の目的です。無駄な経費を増やして税金が減っても、手元のお金が減っていれば意味がありません。
また、社員への賞与や役員報酬の調整も、短期的な節税にとらわれすぎると逆効果になるケースがあります。特に役員報酬の増減は、翌年度以降の資金繰りや社会保険料に直結するため、慎重な判断が求められます。
(2) 必要な支出を“未来への投資”に変える
どうせ使うなら、「キャッシュフロー改善」「売上増」「利益増」につながることにお金を使いましょう。節税は手段であり、目的ではありません。
例えば、営業活動の効率化につながるITツールへの投資、オンラインマーケティングの強化、人材育成や社内制度整備などは、長期的な利益改善につながる可能性があります。こうした未来志向の支出は、たとえ一時的にキャッシュアウトしても、将来のキャッシュインを生み出す投資と見なすことができます。
(3) 節税よりも「回収」を意識する
売掛金の回収サイトを短縮したり、在庫を減らすことで、手元資金は大きく改善します。節税ばかりに目が向くと、こういった本質的な改善がおろそかになります。
資金繰りの根本的な改善には、「どこでお金が滞留しているのか」を把握することが必要です。
売上が立っていても、現金化されなければ意味がありません。売掛金の管理ルールを見直す、在庫管理を徹底する、サブスクモデルや前受金モデルの導入を検討するなど、キャッシュインのスピードを上げる工夫をしましょう。
まとめ:本当に得する節税とは何か?
・節税は「お金を使うこと」ではなく「お金を残すこと」である
・利益と現金のズレを正しく理解しなければ、本質的な手元資金の改善はできない
・節税策は「未来への投資」に繋がるものを優先すべき
キャッシュを残す節税とは、「今だけを見ず、未来も含めて最も資金効率のよい支出の形を考えること」です。
中小企業の経営は、目の前の利益だけでなく、2年後、3年後に向けた体質改善が求められます。
そのためには、税金をコストとしてただ削るのではなく、「利益をどうつくり、どう使うか」という視点での判断が欠かせません。
目の前の節税効果に目を奪われず、「このお金は将来、自分の会社を強くするか?」という問いを常に持ち続けてください。
それこそが、キャッシュが残る、本当に意味のある節税戦略です。