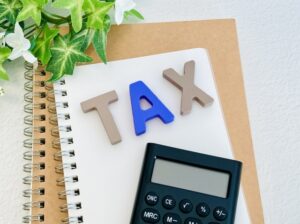利益を上げずに手元にお金を残す方法

――人間関係の力で実現する“見えない節税術”
はじめに:「儲けているのに、お金がない」会社の正体
「利益は出ているのに、手元にお金が残らない」
「税金だけ増えて、資金繰りが苦しい」
これ、珍しい話ではありません。
むしろ多くの中小企業が抱えている“経営のリアル”です。
ここで大事なのは、「利益=お金が残る」ではないということ。
むしろ、“利益は出さずに、キャッシュを残す”方が経営的には強いのです。
本記事では、会計上の利益にこだわらず、
「人との関係性」を活かしてキャッシュを最大限に残す方法をお伝えします。
結論:利益を出さなくても、お金は残せる
どういうことか?
- 利益は“会計上の数字”で、課税対象になる
- キャッシュは“実際に使えるお金”で、自由に動かせる
つまり、「お金はあるのに税金は最小限」という状態をつくるのが、最強の財務設計なのです。
そして、その実現には「制度」以上に、“人間関係の力”が必要です。
利益を出さずにキャッシュを残す、4つの原則
① 「経費」を増やすのではなく「協力」でコストを減らす
ムダな経費を使って節税するのは、結局お金が減るだけ。
それよりも、「協力によってコスト自体を下げる」ほうがキャッシュ効率が良いです。
例:
- 外注先と信頼関係を築き、費用を抑える
- 社員が工夫して無駄を減らしてくれる
- 税理士が自発的に有利な制度を紹介してくれる
→ 信頼関係があると、“支出を減らせる”のでキャッシュを残すことができます。
② 「先に払って、後で仕事」モデルにする
通常の取引では、「仕事してから報酬をもらう」が一般的。
でも、信頼関係があると「前払い」も可能になります。
例:
- サブスク・顧問契約 → 月初入金
- 契約時に半年分一括入金
これにより、資金繰りが圧倒的にラクになります。
利益はその年に分散計上できることもあり、税金は最低限、キャッシュは手元にという構造が作れます。
③ 節税の「受け皿」を早めに準備する
利益計画を図る上で、節税商品・制度を使う場合、重要なのはタイミングです。
信頼関係があると、税理士や金融機関が先に情報を出してくれるため、準備が可能になります。
- 小規模企業共済(年額84万円)
- 退職金制度の積立
- 倒産防止共済(最大800万円)
- 法人保険の損金計上
- 福利厚生の拡充
→ こうした制度は、「利益を削る」ためにあります
→ 「知らなかった」「遅かった」では適用できません
→ 関係性が整っている人ほど、タイムリーに節税を実行できます
④ 利益を「使う」代わりに「人に回す」
利益を削るために無理な買い物をするのではなく、
信頼できる人にお金を“預ける”形で、利益を減らすことができます。
例:
- 社員への賞与(ただし意図を説明し、モチベーションUPにつなげる)
- 家族への給与(仕事内容を明確にする)
- 社員の外部研修受講費を負担(社員のスキルアップを支援)
→ これらはすべて「経費」になる
→ しかも、人間関係が深まる=次年度以降の収益性・安定性が上がります
【比較】“制度だけで節税”vs“人間関係で節税”
| 項目 | 制度だけ | 人間関係も活かす |
|---|---|---|
| 知識 | 取捨選択が困難 | 必要なものだけ適切に入る |
| タイミング | 遅れることが多い | 先回りで打てる |
| 実行力 | 手続きが重くなる | 協力が得られるのでスムーズ |
| 結果 | 利益は消えても、お金も出ていく | 利益は消えて、お金は残る |
利益を残さず、お金を残す設計シート(5ステップ)
- 年間の想定利益をざっくり試算
- 共済・保険・退職金など「使える制度の上限」を確認
- 社員・家族・外注など“信頼できる相手”への支払い設計
- 「事前」に税理士と打ち合わせを行うタイミングを確保
- 前払い・継続契約など「キャッシュを先に入れる仕組み」を整備
まとめ:人間関係が整えば、税金はコントロールできる
節税とは、数字の操作ではありません。
それは、**信頼の上に成り立つ“経営判断”**です。
- 協力してくれる税理士
- 応援してくれる銀行
- 理解してくれる社員
- 誠実な外注先
- 家族との連携
これらがそろえば、
「利益は出ていない、でもお金はある」
そんな経営体質も実現できます。